と言っても基本的な事なのですが…。
和音の名前のところで出てきた
「どの音でもそれを最初の [1] として番号を…」
を、もう一度考えて下さい。
ド を 1 とする 1、3、5 は「C」か「Cm」
レ を 1 とする 1、3、5 は「D」か「Dm」
ミ を 1 とする 1、3、5 は「E」か「Em」
ファ を 1 とする 1、3、5 は「F」か「Fm」
ソ を 1 とする 1、3、5 は「G」か「Gm」
ラ を 1 とする 1、3、5 は「A」か「Am」
シ を 1 とする 1、3、5 は「B」か「Bm」
でしたね。
ところでこの ドレミファソラシド は一回りだけでなく、その前後にも同じように存在します。
たとえば五つの奇数番目を考える時には後に付け足して
「ドレミファソラシドレミファソラシド」としました。
同じように前にも付け足して
「ドレミファソラシドレミファソラシドレミファソラシド」
当然、さらにその前後にもあります。
これを一直線に並べようとするととんでもない事になります。
それはスケールには 始めも終わりも無い からなのです。
「人間が聞こえる限界音」とか「楽器(という道具)が出せる限界音」は確かにありますが
思考の上では無限に続いてしまいます。
ちょっと意地悪な質問をしますよ。
「ド」と「ソ」はどちらが高い音?
「ドレミファソラシ」の中で考えれば答は「ソ」なのですが
「ドレミファソラシド」の中で考えると…
へへへ、もうおわかりですね。
「ソ」より低い「ド」も、高い「ド」もありますからこの質問の形では答が出ません。
このように無限に続く状態を表記するには1次元の直線上では無理です。
では、どうすると良いでしょう?
こうしましょう。
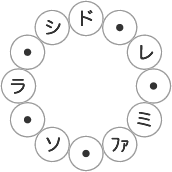 |
そして、それぞれを1とする1、3、5のコードに置き換えてみると
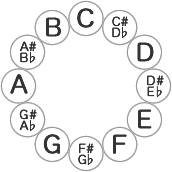 |
この形を覚えておいて下さい。
※ ワープロ入力の際「♭」は全角しかありませんが、半角のアルファベットと組み合わせる時は面倒です。
そんな時はよく似ている Bの小文字「b」(半角)を使ってみましょう。
歌詞カードなどを作るときには重宝しますよ
ところで、今までの 音楽(音学だったかもしれませんが)の授業で「主要三和音」というのを聞いた事はありませんか?
これは「ほとんどのメロディーは伴奏を三つの主な和音でまかなえる」というちょっと強引なルールです。
音楽そのものが複雑になってきている昨今では無理がありますが、基本の部分なのでお付き合い下さい。
曲が ド を1とする メジャースケール で構成されている時
おそらくその曲はCのコードを軸にして展開されています。
Cひとつで伴奏が成立するかもしれません。 もしくはCとあと何かひとつ。 あるいはCとあとふたつ。 または…
このCを軸にして伴奏が展開されている時に、その曲のキーを「C」と呼びます。
その曲はCのコードをメインで使っているんだな…と思ってください。
このコードは名前を考える時に使った音階 12345678 の1、3、5を使っています。
ですからメロディーが「ド」か「ミ」か「ソ」だったらCを伴奏に使えます。
ところが1、3、5ではない レ、ファ、ラ、シ のどれかだと伴奏にはCが使えません。
どうしましょうねぇ…。
…って、Cではないコードを当てはめれば良い事なので考えてみましょう。
まず
|
|||||||||||||||||||||||
「12345678」
いくつかのプランがありますが、ここでは4から始まる1、3、5のコードを考えます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「12345678」
次に5から始まる1、3、5のコードを考えます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ならば、後ろに付け足してみましょう。
8と、付け足す1は重ねてください。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このように、この三種類のコードのどれかを使えば伴奏が成立するので、この三つのコードを「主要三和音」と言います。
そして、1から始まる1、3、5のコードを 1度のコード(トニック とも呼ばれます)
5から新しく始まる1、3、5のコードを 5度のコード(ドミナント とも呼ばれます)
4から新しく始まる1、3、5のコードを 4度のコード(サブドミナント とも呼ばれます)
と呼びます。
実際のコードに置き換えてみますね。
1度のコード が「C」の時(曲のキーが「C」の時)
5度のコード は「G」(「ソ」から始まる1、3、5だから「G」)
4度のコード は「F」(「ファ」から始まる1、3、5だから「F」)
ということで、この三つがセットで「主要三和音」になります。
この「主要三和音」は「スリーコード」とも呼ばれます。
「C のスリーコードは C、F、G」なんて言葉、聞いた事ありませんか?
では、「G」のスリーコードは? …「G、C、D」
「D」のスリーコードは? …「D、G、A」
「A」のスリーコードは? …「A、D、E」…
ここで、先程覚えておいてくださいと言った円形の図を見てください。
一部分ですが、それぞれのコードはお互いにスリーコードの要素になっているのが解ると思います。
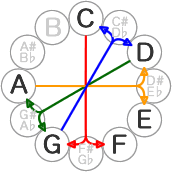 |
離れていると見にくいのでスリーコードがお互いに隣同士になるように並べ替えてみましょう。
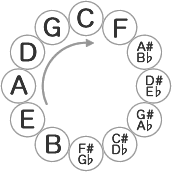 |
この図が「Circle of Fifth」と呼ばれるものです。
不思議な事にいろいろなコードを鳴らしていると、矢印の向きにコードが 進みたがり ます。
(聞いていると「安定」していくように聞こえる…と言う方が良いかな?)
少なくとも、曲の 最後の二つ のコードが矢印のように進行すると「終わる」感じになります。
意外にこの順番でコードが並ぶ事が多いので、覚えておくと便利ですよ。
(もちろん絶対的なものではありません。わざと逆行する曲もありますからねー)
次に続く…