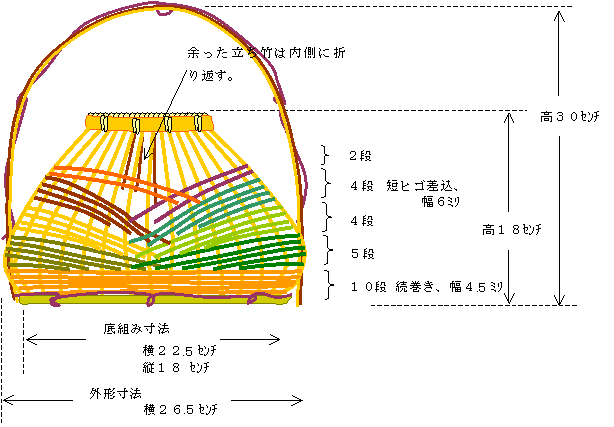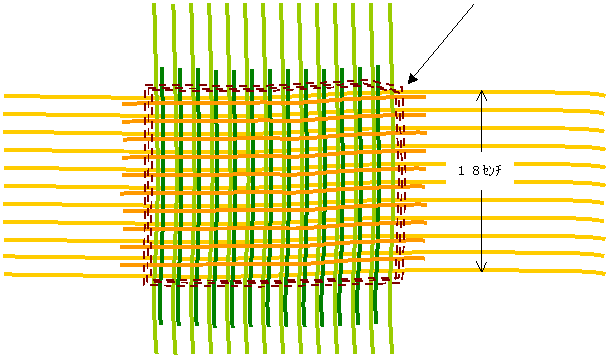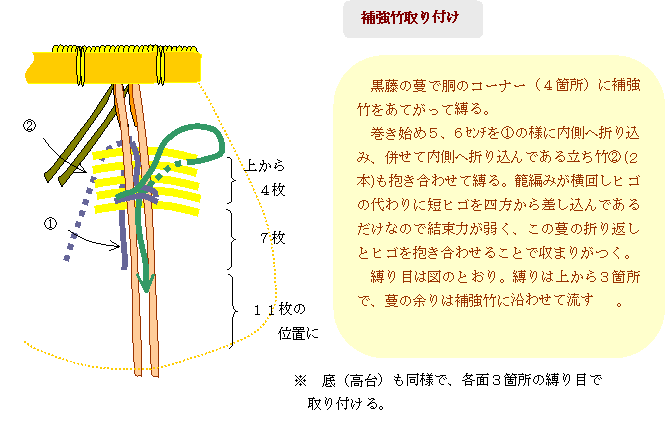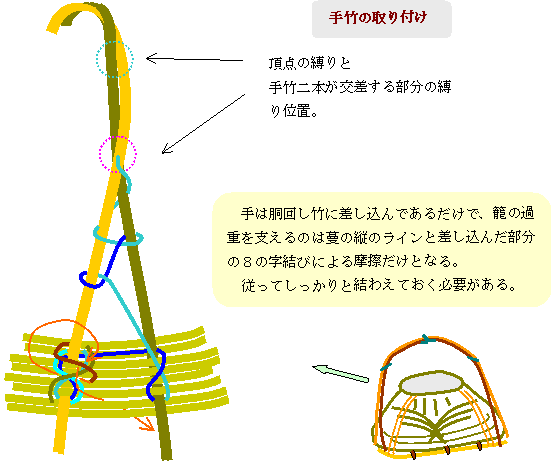|
底組み
立ち竹は、幅は5ミリ、11×13本で底組する。二目飛び二目すくい。組んだ後で更に挿込み竹を挿入する。(縦横で22本)
外周を細ヒゴで3~4周して形を整える。
出来上がりの姿をゆったりとさせるため、横回しのヒゴは締めすぎないように。
写真は横回しを4段くらい編んだところ |
 |
横回し完了
締めすぎないようにと言うより、ユル褌(フン)状態くらいの方がいいでしょう。
編み目は二目押さえの二目掬いで進めますが、立ち竹は当然偶数ですので、一周する間に一箇所だけ一目にして、編み目がずれるようにします。
10段回してひとまず終了です。
写真下方のヒゴは次の工程のコーナーの差込竹です。適当に竹の節芽も残して「味といいますか景色と言いますか、」 籠がのっぺらぼーにならないように配慮します。 |
 |
差し込み編み 【正面】
写真は下から5段、4段が済んで次の4段の一本目を差し込む位置です。
初めの5段は、コーナーの立ち竹から数えて3本目の立ち竹を押える位置から基本的には2目飛びで編みますが、立ち竹が縦に2目で表裏になるようにするため、適宜1目、或いは3目飛びを配して差し込みます。 |
 |
【側面】
写真左半分を見て、
最初の5段の3本目が側面の中央の立ち竹を跨いだら、4本目は一旦立ち竹3本分戻って納め、5本目と続ける。
・・・・・・・・・
同様の作業を対角のコーナーで行う。
写真右半分を見て、
残る2コーナーは籠の側面から始まるが、コーナーの立ち竹から数えて2本目を押える位置から始める。
編み目の飛び方は前記に準ずる。
ヒゴの仕舞いの重なり具合は、正面図の左部分のようにヒゴを始末するが、結果的に側面図で見るのと同様である。 |
 |
5段、4コーナー(一回り)が済んだら次は4段を2回、このとき差し込み始めの部分は5段の時の1目中心寄りである。・・・最初の5段の2本目から5本までの4本分と同様の軌跡となる。
4段が二回り済んだら最後は2段で仕上げるが、編み込みの仕舞い部分を写真のように飛ばして編み上がりとなる。
これで籠本体の編みは終了します。 |
 |
立ち竹の縛り
立ち竹の余った部分は切り捨てずに内側に折り込み、タコ糸で縛ります。
中枠を先に作って仮にあてがい、各立ち竹に印を付けておいてから折り込むようにすると形が整います。
|
 |
縁仕上げ
外枠、中枠を作って籐で縛ります。
糸の縛り目は見えていて構いません。
これで籠本体が出来上がりました。 |